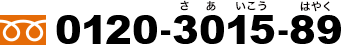労働時間と生産性の関係ついて考える。
基本比例はしている。
人間はある程度の連続時間で生産効率は落ちてくるが、生産性が原則マイナスにはならない。
残業は昨今悪のように言われる。
しかし、8時間労働が10時間になった時点で生産性がどれくらい落ちるのかは個人差である。
生産性は落ちたとしても、必ず前には進む。
そもそもの量をさばかないといけない時はそれが求めれる。
5時間で働いたからといって生産性が上がるわけではない。
それが2時間でも同じ。7時間でも同じ。
8時間労働が最適というのはおそらく後付け理論ではあろう。1日が24時間なので8時間と定めたか。
残業は生産効率を下げながら、それでも生産をし続ける仕組み。
それとは異なり、休日出勤の生産効率は優れている。
補足するが、途方もない毎日の残業時間、その上で休日も返上しての労働を指しているのではない。
それは過労死します。
適度な毎日の労働。8時間プラス、3×6協定の範囲内での労働時間に週に2日の休み。
この2日の休みのどちらも、またどちらか、またその一部を労働に充てることは高い生産性をもたらす。
そもそも週休2日という制度はここ10年、20年のものだ。
私が小学生の時は土曜日は3時間目まであった。今は土曜日は休日。しかし、私学は土曜日も普通にやっているではないか。ちなみに海外も。
勝っているところは週休2日ではない。これは1つのヒントになる。
話を戻すが、週に1日休み、休み1日の全部、またはその半分や一部を労働時間に充てると生産性はグンと上がる。
現場などで例えたら分かりやすいだろう。
職人が週2回現場を空けると、週に6日×7時間の42時間分進むところが、5日×7時間の35時間になり、生産性は20%弱も下がる。
現状、現場を週1の休みにしているのは、全体の20%の生産性を維持するためと言える。その上であらゆることは成り立っている。
結論ではないが、労働時間と生産性、生産性を上げたければまず時間だ。時間は裏切らない。
健康を損なわない程度に、長くした労働時間は、生産性をより求めるときには即効性がある。
効率を求めるなら残業ではなく、休日か。
これは自分の経験でも同じだ。やはり、よく寝て、休みの日に出勤すると進む。効率も全然悪くない。
そう考えていくと、人間ではなく、機械がベストではないか。AIをはじめとするコンピュータは8時間労働など概念もない。
夜中もやるし、休みも与えなくていい。
人は人にしか出来ない仕事にますますシフトしないと、これまでの話から勝ち目はないか。
そういえばうちのコインランドリーはずっと売ってくれている。
1ヶ月が31日間の月は、30日間の月より確実に1日分売上は増える。
これが労働時間と生産性の関係の今日の結論かな。もっと考えていきたい。
2023年11月06日
労働時間と生産性の関係
posted by orangeknight at 12:16
2023年11月05日
第17期がはじまって5日が過ぎた
次のチラシ、そして同じく来月のDMの原稿が出来上がった。締切より2日早い。満足。今期は余裕をもってやるんだ。
今年は、いや新年会だから来年だ。1月で新年会と協力業者会をやる。決めました。
リフォーム業っていうのは、人と拠点を増やせば数字は増える。しかし、それとと共に顧客満足が目的だという、エッセンスは薄れていく。うちでも昔そういうことがあった。
でも、もう同じことは繰り返さない。自分の理想は妥協しない。
金土でやった「トイレ交換即売会」良かった。2日間で行ったのが成功の要因なのです。
不動産をネットで探す。今日など3時間はやっている。なかなかない。でも、私がリフォームさせていただいたおうちが2件売られていたのを見つけた。あの内装の写真は、と当時の思い出はよみがえる。そして、永遠などない。お疲れ様でしたと思った。
会社の前に車を停めないのかとよく尋ねられる。はい、なんの得にもなりませんからと回答する。このくだり、何回したか。
ベンツを会社の前に停めて、BtoCでやっている企業にメリットはない。いや、デメリットしかない。なので置く必要などない。
ブランディングは徹底が要諦だ。
前回工事をさせていただいたお客様から、また今回発注いただく。その際、相見積りがなく、単独で指名していただけること。これがリフォームの営業担当者としての最大の誉(ほまれ)である。
オレンジナイトではそう考えているし、そう指導している。それ以上のものはありますかと。そうならないとと。
先月読んだ本に2050年にスマホなど無くなると書かれていた。当然パソコンも。普及率は0%だと。
代わりにスマートグラス(メガネタイプ)、スマートコンタクト(コンタクレンズタイプ)、さらには振動などで触覚を疑似的に再現するハプティクスというものが広まると。
同じことをしていたらいかん。日々進化。
インプットしていかないと時代に淘汰される。いつもそうおそれている。
前にも書いたが、退場は自分で決めたい。
淘汰されての退場はまっぴらごめんだ。
その為にしがみつくんだ。その時まで振り落とされないように、勉強して考えて、そして行動して。
良い仕事をしてもらったと、自分以外の人間のことで褒めていただくこと。社員、職人問わず嬉しい。自分が褒められる数倍嬉しい。そういうものだ。
今年は、いや新年会だから来年だ。1月で新年会と協力業者会をやる。決めました。
リフォーム業っていうのは、人と拠点を増やせば数字は増える。しかし、それとと共に顧客満足が目的だという、エッセンスは薄れていく。うちでも昔そういうことがあった。
でも、もう同じことは繰り返さない。自分の理想は妥協しない。
金土でやった「トイレ交換即売会」良かった。2日間で行ったのが成功の要因なのです。
不動産をネットで探す。今日など3時間はやっている。なかなかない。でも、私がリフォームさせていただいたおうちが2件売られていたのを見つけた。あの内装の写真は、と当時の思い出はよみがえる。そして、永遠などない。お疲れ様でしたと思った。
会社の前に車を停めないのかとよく尋ねられる。はい、なんの得にもなりませんからと回答する。このくだり、何回したか。
ベンツを会社の前に停めて、BtoCでやっている企業にメリットはない。いや、デメリットしかない。なので置く必要などない。
ブランディングは徹底が要諦だ。
前回工事をさせていただいたお客様から、また今回発注いただく。その際、相見積りがなく、単独で指名していただけること。これがリフォームの営業担当者としての最大の誉(ほまれ)である。
オレンジナイトではそう考えているし、そう指導している。それ以上のものはありますかと。そうならないとと。
先月読んだ本に2050年にスマホなど無くなると書かれていた。当然パソコンも。普及率は0%だと。
代わりにスマートグラス(メガネタイプ)、スマートコンタクト(コンタクレンズタイプ)、さらには振動などで触覚を疑似的に再現するハプティクスというものが広まると。
同じことをしていたらいかん。日々進化。
インプットしていかないと時代に淘汰される。いつもそうおそれている。
前にも書いたが、退場は自分で決めたい。
淘汰されての退場はまっぴらごめんだ。
その為にしがみつくんだ。その時まで振り落とされないように、勉強して考えて、そして行動して。
良い仕事をしてもらったと、自分以外の人間のことで褒めていただくこと。社員、職人問わず嬉しい。自分が褒められる数倍嬉しい。そういうものだ。
posted by orangeknight at 16:16
2023年11月04日
「税理士に相談する」は意外と多い
会社で何かを購入したり、契約するとき「税理士に相談する」経営者は意外と多い。
私は全く相談しない。
いや、したことがない。というか、何を相談するかも理解し難い。
試算表から今期の経費になるのかとか、どういう償却をされるのかなど聞くのか。
はたまた「こういうふうにしようと思っているんだが、先生どう思う?」とアドバイスを求めるか。
こういうふうな取得方法をすれば節税になる、とかを教えてもらっているのかな。
うちの顧問税理士とそういう話をすると、笑いながら「聞いてこられる方もたくさんいますよ」と言う。
多分その笑いは、魚住は全くそれがないねを表していると思うがスルーする。
でも、会社のことを朝から晩まで考えているのは社長だけで、命と言っても過言ではないリスクがかかっているのも社長だけである。
それをたくさんの顧問先を持つ税理士に、都度確認しても、ベストなアンサーが導かれるとは思えないのだが、どうなのだろう。
専門的な知見をいただくのはブレーントして存在してもらっているので必要不可欠だと思う。
しかし、買ったり契約するのは、社長の勘でスピーディーに行うのが最高だと思うのだが。
誰にも相談しないで決めるから一瞬で決まる。
パッパパッパと進んでいく。
判断の成功率は、より高いものが当然求めれるが、それが能力というものだ。
なんで「税理士に、税理士に〜」と言う人が多いのかなと思う。
あなたの子供と同じくらい、大切に想っている会社のこと、そこまで顧問税理士は考えていないのになぁと思う。
もちろん優秀な方々なのですが。
私は全く相談しない。
いや、したことがない。というか、何を相談するかも理解し難い。
試算表から今期の経費になるのかとか、どういう償却をされるのかなど聞くのか。
はたまた「こういうふうにしようと思っているんだが、先生どう思う?」とアドバイスを求めるか。
こういうふうな取得方法をすれば節税になる、とかを教えてもらっているのかな。
うちの顧問税理士とそういう話をすると、笑いながら「聞いてこられる方もたくさんいますよ」と言う。
多分その笑いは、魚住は全くそれがないねを表していると思うがスルーする。
でも、会社のことを朝から晩まで考えているのは社長だけで、命と言っても過言ではないリスクがかかっているのも社長だけである。
それをたくさんの顧問先を持つ税理士に、都度確認しても、ベストなアンサーが導かれるとは思えないのだが、どうなのだろう。
専門的な知見をいただくのはブレーントして存在してもらっているので必要不可欠だと思う。
しかし、買ったり契約するのは、社長の勘でスピーディーに行うのが最高だと思うのだが。
誰にも相談しないで決めるから一瞬で決まる。
パッパパッパと進んでいく。
判断の成功率は、より高いものが当然求めれるが、それが能力というものだ。
なんで「税理士に、税理士に〜」と言う人が多いのかなと思う。
あなたの子供と同じくらい、大切に想っている会社のこと、そこまで顧問税理士は考えていないのになぁと思う。
もちろん優秀な方々なのですが。
posted by orangeknight at 11:25
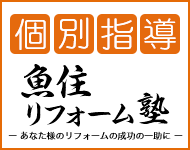
-
Twitter
-
最近の記事
- (02/18) 学校にエアコンなかったなぁ
- (02/17) ダイキンのRXシリーズがいい!
- (02/16) 子供のビデオ鑑賞
- (02/15) 提案させてほしい工事の一つ
- (02/14) 子供じゃないんですから!
- (02/14) かっこいい女
- (02/14) 和室改装の着工
- (02/13) ちょっと年をとりわかりかけたこと
- (02/12) 「今のご不満解決シート」投入
- (02/11) もうすぐ3年のオレンジナイト赤穂店
- (02/10) 呑んでも呑まれるな
- (02/07) 本社ショールームの地質調査
- (02/06) LIXILの表彰式に行く
- (02/04) 今年の豆まき
- (02/03) 鼻マスクをいただく
- (02/02) 大阪、神戸でショールーム見学
- (02/01) テロの発生理由
- (01/31) オーシャンブルーに屋根塗装
- (01/31) 省エネ住宅ポイントお問合せ
- (01/30) 仕事は結果、勉強は家で
-
過去ログ
- 2025年4月 (19)
- 2025年3月 (35)
- 2025年2月 (34)
- 2025年1月 (30)
- 2024年12月 (41)
- 2024年11月 (32)
- 2024年10月 (35)
- 2024年9月 (42)
- 2024年8月 (30)
- 2024年7月 (40)
- 2024年6月 (41)
- 2024年5月 (35)
- 2024年4月 (42)
- 2024年3月 (53)
- 2024年2月 (39)
- 2024年1月 (37)
- 2023年12月 (40)
- 2023年11月 (35)
- 2023年10月 (33)
- 2023年9月 (39)
- 2023年8月 (36)
- 2023年7月 (37)
- 2023年6月 (42)
- 2023年5月 (32)
- 2023年4月 (31)
- 2023年3月 (38)
- 2023年2月 (32)
- 2023年1月 (31)
- 2022年12月 (36)
- 2022年11月 (34)
- 2022年10月 (28)
- 2022年9月 (27)
- 2022年8月 (30)
- 2022年7月 (32)
- 2022年6月 (40)
- 2022年5月 (21)
- 2022年4月 (34)
- 2022年3月 (40)
- 2022年2月 (31)
- 2022年1月 (34)
- 2021年12月 (35)
- 2021年11月 (32)
- 2021年10月 (34)
- 2021年9月 (39)
- 2021年8月 (35)
- 2021年7月 (42)
- 2021年6月 (30)
- 2021年5月 (28)
- 2021年4月 (30)
- 2021年3月 (29)
- 2021年2月 (34)
- 2021年1月 (37)
- 2020年12月 (38)
- 2020年11月 (38)
- 2020年10月 (36)
- 2020年9月 (32)
- 2020年8月 (36)
- 2020年7月 (34)
- 2020年6月 (36)
- 2020年5月 (39)
- 2020年4月 (43)
- 2020年3月 (40)
- 2020年2月 (36)
- 2020年1月 (34)
- 2019年12月 (37)
- 2019年11月 (28)
- 2019年10月 (30)
- 2019年9月 (43)
- 2019年8月 (33)
- 2019年7月 (34)
- 2019年6月 (34)
- 2019年5月 (25)
- 2019年4月 (29)
- 2019年3月 (37)
- 2019年2月 (34)
- 2019年1月 (28)
- 2018年12月 (32)
- 2018年11月 (31)
- 2018年10月 (34)
- 2018年9月 (37)
- 2018年8月 (29)
- 2018年7月 (39)
- 2018年6月 (40)
- 2018年5月 (34)
- 2018年4月 (35)
- 2018年3月 (34)
- 2018年2月 (25)
- 2018年1月 (31)
- 2017年12月 (29)
- 2017年11月 (31)
- 2017年10月 (30)
- 2017年9月 (33)
- 2017年8月 (39)
- 2017年7月 (39)
- 2017年6月 (35)
- 2017年5月 (40)
- 2017年4月 (42)
- 2017年3月 (34)
- 2017年2月 (41)
- 2017年1月 (41)
- 2016年12月 (40)
- 2016年11月 (35)
- 2016年10月 (37)
- 2016年9月 (43)
- 2016年8月 (49)
- 2016年7月 (38)
- 2016年6月 (44)
- 2016年5月 (46)
- 2016年4月 (41)
- 2016年3月 (43)
- 2016年2月 (41)
- 2016年1月 (43)
- 2015年12月 (43)
- 2015年11月 (45)
- 2015年10月 (41)
- 2015年9月 (36)
- 2015年8月 (36)
- 2015年7月 (33)
- 2015年6月 (23)
- 2015年5月 (30)
- 2015年4月 (34)
- 2015年3月 (38)
- 2015年2月 (26)
- 2015年1月 (27)
- 2014年12月 (28)
- 2014年11月 (31)
- 2014年10月 (20)
- 2014年9月 (21)
- 2014年8月 (21)
- 2014年7月 (26)
- 2014年6月 (23)
- 2014年5月 (21)
- 2014年4月 (22)
- 2014年3月 (22)
- 2014年2月 (21)
- 2014年1月 (20)
- 2013年12月 (22)
- 2013年11月 (22)
- 2013年10月 (22)
- 2013年9月 (26)
- 2013年8月 (25)
- 2013年7月 (27)
- 2013年6月 (31)
- 2013年5月 (31)
- 2013年4月 (35)
- 2013年3月 (33)
- 2013年2月 (29)
- 2013年1月 (38)
- 2012年12月 (30)
- 2012年11月 (35)
- 2012年10月 (34)
- 2012年9月 (35)
- 2012年8月 (30)
- 2012年7月 (39)
- 2012年6月 (29)
- 2012年5月 (31)
- 2012年4月 (38)
- 2012年3月 (33)
- 2012年2月 (29)
- 2012年1月 (27)
- 2011年12月 (24)
- 2011年11月 (31)
- 2011年10月 (25)
- 2011年9月 (27)
- 2011年8月 (26)
- 2011年7月 (42)
- 2011年6月 (2)