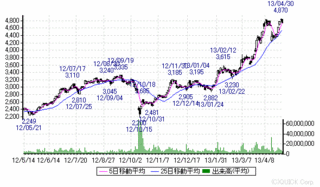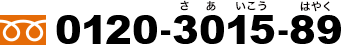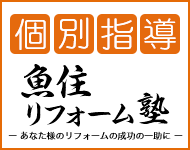結論から言いますと今日全て売りました。
前回までの経緯ですが、僕はソフトバンクがアメリカの会社をM&Aすると発表したときに「なんて孫さんってかっこいい人なんだろう、男子として生まれたからには1番にならないとって、孫さんが言うと感動を通り越してしびれるわ!」と思い、応援する意味でその時期イマイチと評価されていたソフトバンク株を300株買いました。
儲かろうが損しようがいいわと思い、純粋にあやかろうと考え買ったので、その時は素人目には「買い」のタイミングではなかったと思います。
それが去年の10月のことで100株(ソフトバンクの単元は100です)2590円でした。
それを300株買いましたので2590円×300株で777000円でした。全体からしたらはなくそみたいな金額でしょうが、役にたてれば嬉しいなと思い買いました。
それからアベノミクスや何やらであれよあれよというまに2590円が4800円をこえるまでに右肩上がりしたのです。
僕が今日売ったのは、正直いつも株価をみているわけではありません。
ここまで上がっているとは思いもよりませんでしたが、昨日ソフトバンクの業績発表があり、それがとても良いものでしたので「そうや!確認しておこう」と思って口座のある証券会社にログインしたんです。
2590円が4820円になっているということは、777000円が1446000円になっているということで669000円の利益です。
前回確認した時が確か48万くらいの利益でしたので、それからもぐいぐい上がったようです。
今月半ばでしたか、デッシュ社がソフトバンクのスプリント社への買収提案に横やりを出してきたときも確認していなかったくらいですので、全くキャピタルゲインに興味はありませんでした。
しかし、今日、朝起きた瞬間「売らなければいけない」という衝動に強くおそわれました。
興味がないといっても利益はお金。60万70万稼ぐのは大変なことです。
ここまで株価があがったということはソフトバンクの時価総額もすごい上がっているはず。そして、絶対はないでしょうがソフトバンクのM&A の優位は変わらないとのこと。
ここは、1度売って様子をみるというのも選択肢の一つではないか、との思いが朝起きた瞬間流れました。
買ったときの考えや、ブログで書いたことなどいろいろ思いはよぎりましたが、前言をすぱっと撤回することも経営者として大切、などと自分を自分で擁護して、午前中に成行きで即座に約定しました。
今後またやはり孫さんを応援したいので買わせていただくと思いますし、利益をださせていただき感謝しています。
まぁ、でもお金って汗して働いてやっと得るものですから、この利益の60数万円は自分ではなくて会社のために使わせてもらおうと思っています。
その内容はまたご報告します。
なんで、朝起きた瞬間そんな強い衝動におそわれたかわかりませんが、本能とか勘とかは大事にする主義なんです(少し罪悪感…)。