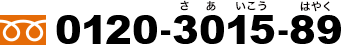僕は会社の事で知らないことはありません。
そんな事はないだろうと思われるかもわかりませんが、オレンジナイトくらいの小さな会社で知らないことがあるようではやっていけないのです。
もちろんそのためには信頼できる部下が何人も何人もいないといけません。
僕の立場、また性格は裸の王様になりやすいので、本当のことを言ってくれる人がいないと致命的なことになります。
もっと言うと会社で起こりうるような事は人からの報告も必要として把握していますが、社員が今何を思っているか、やる気が出ているか、士気が上がっているか、はたまた悩んでいるか、気持ちが離れていっているかは誰かを通じなくても分かります。好きの度合いなど完全に分かります。特に異性である女子は分かりやすい。
こういったことを理解いただける人はたくさんいると思いますが、そうでないと人はついて来てくれません。
みんな分かってほしいと心の中で思っています。
分かってくれているだろうと自分の心を慰めて気持ちをおさめるものでしょう。
そこで、僕が鈍感なら必ず部下は悲しくなり、僕が逆の立場なら拠り所がほしいと願います。
「目は口ほどに物を言う」ということわざがあります。
昔の人は本当によく言ったもので、そこが一番感じるところです。
社内で起こる出来事は全て自分の力だけで把握できませんが、人の気持ちがわかるのはそこなんでしょうね。
朝の「おはようございます」や、帰りの「お疲れ様でした」は正直なものなのです。
多分世の中のたくさんの、部下を持つ人々は同じ事を思っていますよね。
2014年03月03日
目は口ほどに物を言う
posted by orangeknight at 21:44
2014年03月01日
理念の再浸透、課の名称変更を
三月が始まりましたね。今月はどんな事がおこるのか、毎日ありますいろんな事。「仕上る」ことは永遠にないでしょうし、日々みんなで切磋琢磨しながら臨んでいきたいと考える月初め。
さぁ、いきます今月も書きます。
今しようとしていることの一つに「課の名称変更」があります。
例えば「営業課」を「〇〇課」にということです。
会社には理念というものがあり、それの持つ力の大小はすなわち会社の全てをあらわすと言えると思います。
理念が形骸化したら社員の心も希薄なものになり、いくら高価な額縁に理念を書いて飾っていても、会社のみんなが会社の理念を理解していなければ何の値打ちもありません。
その理念の再浸透の一環として「課の名称変更」をすることにしたんです。
「営業課」や「施工管理課」「総務課」など、他にもありますがオレンジナイトにはこのような名称の課があります。
しかし、よくよく考えればです、営業マンは営業活動をすることが仕事ではないことに気づきました。
言わばそれは過程であって、その先にあるもの、例えば受注し、オレンジナイトのサービスを提供してお客様に喜んでいただくこと、便利だと感じていただくことなどが目的であり、それこそが課の名称に値しないと、そこの部署に所属する社員の存在意義(理念)が明確化されないんではないかと感じました。
「営業課」だと営業活動することに存在意義が出てしまう。それは違いますよね。
「施工管理課」は施工管理することに存在意義が出てしまう。あくまで施工管理は過程であり、何のために彼ら彼女らがいるのかと考えれば、施工管理するためにいるのではなく、きちんとした工事を提供し、営業だけでは満足なサービスも提供できないことがあるので、そこを協力して顧客満足度を高めるのが目的。なので、名称は「施工管理課」ではなく例えばですが「顧客満足高める課」とかがふさわしいと思います。
「何のために仕事をしているのか」ということがなかなかはっきりと言える人は少ないと感じます。
お客様や協力業者様そして会社から、社員みんなが自分自身に求められていることをもっと理解したら、これは仕事そのものが変わりますしそこが本質であります。
営業活動は過程、事務処理は過程、広報は過程。オレンジナイトの各課の行き着くところは同じ。これがベクトルが揃うということであります。
今まだ検討中、会社のみんなから募集中ですが、すごく仕事に影響がでてくるはずです。じわじわじわじわ効いてきます。
たかが名称ですが、名前はすごい力を持っています。
拠り所、存在意義、理念、本当に大切だと感じています。
さぁ、いきます今月も書きます。
今しようとしていることの一つに「課の名称変更」があります。
例えば「営業課」を「〇〇課」にということです。
会社には理念というものがあり、それの持つ力の大小はすなわち会社の全てをあらわすと言えると思います。
理念が形骸化したら社員の心も希薄なものになり、いくら高価な額縁に理念を書いて飾っていても、会社のみんなが会社の理念を理解していなければ何の値打ちもありません。
その理念の再浸透の一環として「課の名称変更」をすることにしたんです。
「営業課」や「施工管理課」「総務課」など、他にもありますがオレンジナイトにはこのような名称の課があります。
しかし、よくよく考えればです、営業マンは営業活動をすることが仕事ではないことに気づきました。
言わばそれは過程であって、その先にあるもの、例えば受注し、オレンジナイトのサービスを提供してお客様に喜んでいただくこと、便利だと感じていただくことなどが目的であり、それこそが課の名称に値しないと、そこの部署に所属する社員の存在意義(理念)が明確化されないんではないかと感じました。
「営業課」だと営業活動することに存在意義が出てしまう。それは違いますよね。
「施工管理課」は施工管理することに存在意義が出てしまう。あくまで施工管理は過程であり、何のために彼ら彼女らがいるのかと考えれば、施工管理するためにいるのではなく、きちんとした工事を提供し、営業だけでは満足なサービスも提供できないことがあるので、そこを協力して顧客満足度を高めるのが目的。なので、名称は「施工管理課」ではなく例えばですが「顧客満足高める課」とかがふさわしいと思います。
「何のために仕事をしているのか」ということがなかなかはっきりと言える人は少ないと感じます。
お客様や協力業者様そして会社から、社員みんなが自分自身に求められていることをもっと理解したら、これは仕事そのものが変わりますしそこが本質であります。
営業活動は過程、事務処理は過程、広報は過程。オレンジナイトの各課の行き着くところは同じ。これがベクトルが揃うということであります。
今まだ検討中、会社のみんなから募集中ですが、すごく仕事に影響がでてくるはずです。じわじわじわじわ効いてきます。
たかが名称ですが、名前はすごい力を持っています。
拠り所、存在意義、理念、本当に大切だと感じています。
posted by orangeknight at 11:37
2014年02月27日
M&Aのセミナーに参加
昨日は午後からヒルトン大阪であったセミナーに参加してきました。
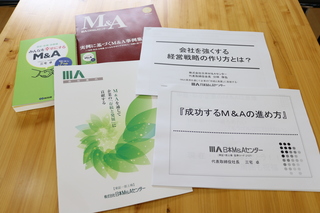
M&Aがテーマで、東証一部に上場されている株式会社日本M&Aセンターさんの主催でした。
最近は毎日のように新聞にはそういう話題が掲載されています。決して大企業だけの話ではなく、昨日のセミナーの中でもありましたが、現在は我々のような会社も頻繁にそれがおこなわれているのが実情です。
昔は企業を買うとか売るとかいう話はさげすまれる傾向にあったと思いますが、昨今はそんな価値観は薄れ、会社を大きくする、存続させる、救済するなどさまざまな理由があるとは思いますが、M&Aという選択肢、手段は僕はありだと思っています。
今回、この分野の話をじかに聞けとても刺激を受けました。
実際に親の代から続く会社を売ったという方の話も聞けました。
僕は買うということを学びたいという概念しか無く参加させていただいたのですが、売る方の状況も知る事ができました。
なんか怖い話ですが最近セミナーでよく耳にする「経営者の行き着くところは夜逃げか自殺」ということを昨日も言っていました。( 苦笑)
非上場企業の倒産はイコール社長の破産を意味すると昨日も聞きましたが、これはその通りだと思いますし、そこは覚悟はあります。リスクはリターンと比例していますから、個人商店の域より大きくオレンジナイトをしようと思った時点から、命を懸けて勝負すると覚悟はしたんですが、「後継ぎ」ということは考えたこともありませんし、僕が今36歳なので普通にいけばまだまだ今からです。
しかし、後継者がいないという中小企業にとって会社の存続は非常に大きな問題。
僕はそれを昨日一番に考えました。
こういう話もあったんですが、例えば社長が70歳で息子がいない。社員はバリバリ働いてくれている。しかし、この先どうしようと社長は考える。
社員の中で継ぎたいと考えてくれる人もいるが、会社の資産価値を換算すると数億円、そして借金もある。
その全てを例え借り入れできる社員はいるはずがない。お金が払えないから売れない。でも社員は一生懸命毎日頑張ってくれている。
そういう時にM&Aという選択肢もあるし、実際息子がいてもそんなリスクを背負いたくないと、後を継がない人が多いので、今売り手もとても多いのだと言われていました。
まだまだ話をしたいことはあるんですが、昨日こう言われていました。
その立場を目指していますので、覚えておこうと思いました。
「中小企業のM&Aでは、絶対に譲渡企業の社員の気持ちを理解しなければならない、創業社長の尊厳を守らなければならない。吸収するという考え方ではなく、共に発展していこうという気持ちがなければ必ずうまくいかない」
その通りだと感じました。
創業者にとって会社は子どもです。社員にとって会社は自分たちが作ってきて、守ってきた、自分たちの会社という自負があります。
「あくまで会社を買っているんではなく、株を買っているんですよ」とも仰っていた。
とても勉強になりました!
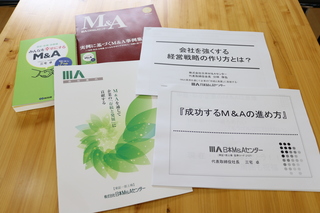
M&Aがテーマで、東証一部に上場されている株式会社日本M&Aセンターさんの主催でした。
最近は毎日のように新聞にはそういう話題が掲載されています。決して大企業だけの話ではなく、昨日のセミナーの中でもありましたが、現在は我々のような会社も頻繁にそれがおこなわれているのが実情です。
昔は企業を買うとか売るとかいう話はさげすまれる傾向にあったと思いますが、昨今はそんな価値観は薄れ、会社を大きくする、存続させる、救済するなどさまざまな理由があるとは思いますが、M&Aという選択肢、手段は僕はありだと思っています。
今回、この分野の話をじかに聞けとても刺激を受けました。
実際に親の代から続く会社を売ったという方の話も聞けました。
僕は買うということを学びたいという概念しか無く参加させていただいたのですが、売る方の状況も知る事ができました。
なんか怖い話ですが最近セミナーでよく耳にする「経営者の行き着くところは夜逃げか自殺」ということを昨日も言っていました。( 苦笑)
非上場企業の倒産はイコール社長の破産を意味すると昨日も聞きましたが、これはその通りだと思いますし、そこは覚悟はあります。リスクはリターンと比例していますから、個人商店の域より大きくオレンジナイトをしようと思った時点から、命を懸けて勝負すると覚悟はしたんですが、「後継ぎ」ということは考えたこともありませんし、僕が今36歳なので普通にいけばまだまだ今からです。
しかし、後継者がいないという中小企業にとって会社の存続は非常に大きな問題。
僕はそれを昨日一番に考えました。
こういう話もあったんですが、例えば社長が70歳で息子がいない。社員はバリバリ働いてくれている。しかし、この先どうしようと社長は考える。
社員の中で継ぎたいと考えてくれる人もいるが、会社の資産価値を換算すると数億円、そして借金もある。
その全てを例え借り入れできる社員はいるはずがない。お金が払えないから売れない。でも社員は一生懸命毎日頑張ってくれている。
そういう時にM&Aという選択肢もあるし、実際息子がいてもそんなリスクを背負いたくないと、後を継がない人が多いので、今売り手もとても多いのだと言われていました。
まだまだ話をしたいことはあるんですが、昨日こう言われていました。
その立場を目指していますので、覚えておこうと思いました。
「中小企業のM&Aでは、絶対に譲渡企業の社員の気持ちを理解しなければならない、創業社長の尊厳を守らなければならない。吸収するという考え方ではなく、共に発展していこうという気持ちがなければ必ずうまくいかない」
その通りだと感じました。
創業者にとって会社は子どもです。社員にとって会社は自分たちが作ってきて、守ってきた、自分たちの会社という自負があります。
「あくまで会社を買っているんではなく、株を買っているんですよ」とも仰っていた。
とても勉強になりました!
posted by orangeknight at 12:08
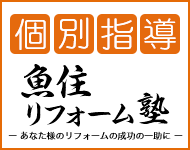
-
Twitter
-
最近の記事
-
過去ログ
- 2025年4月 (7)
- 2025年3月 (35)
- 2025年2月 (34)
- 2025年1月 (30)
- 2024年12月 (41)
- 2024年11月 (32)
- 2024年10月 (35)
- 2024年9月 (42)
- 2024年8月 (30)
- 2024年7月 (40)
- 2024年6月 (41)
- 2024年5月 (35)
- 2024年4月 (42)
- 2024年3月 (53)
- 2024年2月 (39)
- 2024年1月 (37)
- 2023年12月 (40)
- 2023年11月 (35)
- 2023年10月 (33)
- 2023年9月 (39)
- 2023年8月 (36)
- 2023年7月 (37)
- 2023年6月 (42)
- 2023年5月 (32)
- 2023年4月 (31)
- 2023年3月 (38)
- 2023年2月 (32)
- 2023年1月 (31)
- 2022年12月 (36)
- 2022年11月 (34)
- 2022年10月 (28)
- 2022年9月 (27)
- 2022年8月 (30)
- 2022年7月 (32)
- 2022年6月 (40)
- 2022年5月 (21)
- 2022年4月 (34)
- 2022年3月 (40)
- 2022年2月 (31)
- 2022年1月 (34)
- 2021年12月 (35)
- 2021年11月 (32)
- 2021年10月 (34)
- 2021年9月 (39)
- 2021年8月 (35)
- 2021年7月 (42)
- 2021年6月 (30)
- 2021年5月 (28)
- 2021年4月 (30)
- 2021年3月 (29)
- 2021年2月 (34)
- 2021年1月 (37)
- 2020年12月 (38)
- 2020年11月 (38)
- 2020年10月 (36)
- 2020年9月 (32)
- 2020年8月 (36)
- 2020年7月 (34)
- 2020年6月 (36)
- 2020年5月 (39)
- 2020年4月 (43)
- 2020年3月 (40)
- 2020年2月 (36)
- 2020年1月 (34)
- 2019年12月 (37)
- 2019年11月 (28)
- 2019年10月 (30)
- 2019年9月 (43)
- 2019年8月 (33)
- 2019年7月 (34)
- 2019年6月 (34)
- 2019年5月 (25)
- 2019年4月 (29)
- 2019年3月 (37)
- 2019年2月 (34)
- 2019年1月 (28)
- 2018年12月 (32)
- 2018年11月 (31)
- 2018年10月 (34)
- 2018年9月 (37)
- 2018年8月 (29)
- 2018年7月 (39)
- 2018年6月 (40)
- 2018年5月 (34)
- 2018年4月 (35)
- 2018年3月 (34)
- 2018年2月 (25)
- 2018年1月 (31)
- 2017年12月 (29)
- 2017年11月 (31)
- 2017年10月 (30)
- 2017年9月 (33)
- 2017年8月 (39)
- 2017年7月 (39)
- 2017年6月 (35)
- 2017年5月 (40)
- 2017年4月 (42)
- 2017年3月 (34)
- 2017年2月 (41)
- 2017年1月 (41)
- 2016年12月 (40)
- 2016年11月 (35)
- 2016年10月 (37)
- 2016年9月 (43)
- 2016年8月 (49)
- 2016年7月 (38)
- 2016年6月 (44)
- 2016年5月 (46)
- 2016年4月 (41)
- 2016年3月 (43)
- 2016年2月 (41)
- 2016年1月 (43)
- 2015年12月 (43)
- 2015年11月 (45)
- 2015年10月 (41)
- 2015年9月 (36)
- 2015年8月 (36)
- 2015年7月 (33)
- 2015年6月 (23)
- 2015年5月 (30)
- 2015年4月 (34)
- 2015年3月 (38)
- 2015年2月 (26)
- 2015年1月 (27)
- 2014年12月 (28)
- 2014年11月 (31)
- 2014年10月 (20)
- 2014年9月 (21)
- 2014年8月 (21)
- 2014年7月 (26)
- 2014年6月 (23)
- 2014年5月 (21)
- 2014年4月 (22)
- 2014年3月 (22)
- 2014年2月 (21)
- 2014年1月 (20)
- 2013年12月 (22)
- 2013年11月 (22)
- 2013年10月 (22)
- 2013年9月 (26)
- 2013年8月 (25)
- 2013年7月 (27)
- 2013年6月 (31)
- 2013年5月 (31)
- 2013年4月 (35)
- 2013年3月 (33)
- 2013年2月 (29)
- 2013年1月 (38)
- 2012年12月 (30)
- 2012年11月 (35)
- 2012年10月 (34)
- 2012年9月 (35)
- 2012年8月 (30)
- 2012年7月 (39)
- 2012年6月 (29)
- 2012年5月 (31)
- 2012年4月 (38)
- 2012年3月 (33)
- 2012年2月 (29)
- 2012年1月 (27)
- 2011年12月 (24)
- 2011年11月 (31)
- 2011年10月 (25)
- 2011年9月 (27)
- 2011年8月 (26)
- 2011年7月 (42)
- 2011年6月 (2)