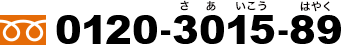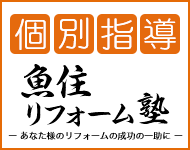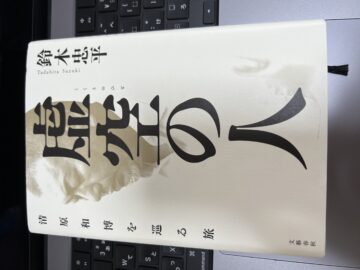
前作の「嫌われた監督」は落合さんのファンなので読んだのですが、鈴木氏の取材力、そして心の内面というか深いところにある闇、また機微を洞察する力に感嘆し、本屋でこの本を目にし即座に手にしました。
今回の「対象」は清原和博さんだった。誰もが知るスター。
清原さんの幼少時からPL学園入学における話、甲子園決勝でのホームラン、桑田さんとのドラフト、そしてプロ野球、覚醒剤から現在までの出来事が、あたかも著者が全て目の当たりにしていたかのように記されていた。
この本を読み、やはりテレビなどでの清原さんは演じられているもので、その内面は全く違うのだなぁと感じた。タイトルにもあるように虚空なのだと。他人が面白く、おかしく感じるのはその瞬間であり、その後は無関心となる。
それが上手く表現されていたのが292ページの岸和田で取材した男たちの言葉であったように思う。
「正直、祭りなんてなんでやっているのか分からんのよ。祭りの日が来るまでは面倒くさいことばっかりや。でもな、だんじり引っ張って、やりまわしを決めた瞬間はシャブなんか比べものにならんくらい気持ちええで。すっこーんて何もかんも吹っ飛ぶ。あの一瞬のためにやっとるんやろうな。そんで祭りが終わったらまた退屈が始まる。もうこんな面倒くさいことやめようかなって思ってる。」
著者は上記の直後にこう記している「もし、清原の人生があの甲子園の決勝戦だけであったなら。ホームランの一瞬だけであったなら。私はそう考えたりもした。だが、祭りが終わったあとも人生は続いていく。だんじりが通り過ぎたあと、ホームランの歓声が消えたあとには平坦な道が残されているだけだ。人はその日常をもがきながら生きていくしかない。」
上手な対比であり、誰しもに同じようにそういうものがあることを表している。
本当に上手い。岸和田での取材はあまり成果が得られなかったように書かれていたが、この一文でアパートを借り、何泊何泊もした甲斐があったなぁと親のように感じた。この一文を感じれる、気付けるのが才能か。
実際に目撃していない過去を、眼前で今起こっているように感じさせるタッチと、その過去に浸っている読者を、一瞬で今現在に戻す文章の書き方がやはり好きだった。
取材をして、こんなふうに書けたらいいなぁ。
羨ましい才能だと感じる1冊でした。