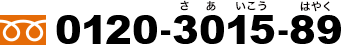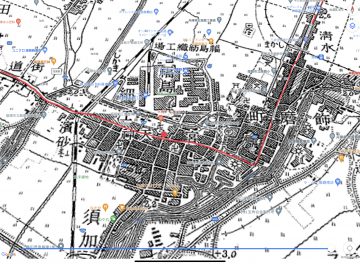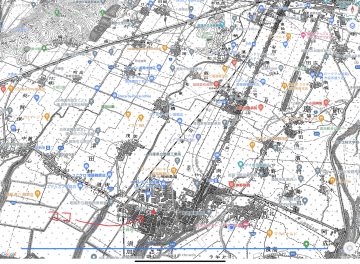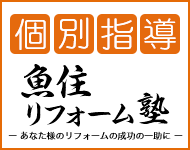そうです、先月外壁塗装した物件です。
どうせならと屋根の漆喰も塗り替えすることにしました。


ちなみに、屋根や壁など、建築で使われる漆喰ってそもそも何か知っていますか。
左官屋さんなどがコテで塗っていますよね。
あれについての話です。
そもそも漆喰は主に石灰石で出来ており、石灰石とはサンゴ礁などから永年かけて生まれたものです。
それを焼いて、砕き、水を加えたものを消石灰と言いますが、それこそが建築で使う漆喰の主な原材料です。
ただ、乾くと固くなり、建築の材料にはもってこいなのですが、それだけでは塗りにくいので、繊維質のものや、より長持ちさせるためにセメントになる材料なども混ぜ、漆喰を作っていっています。
これは職人さんによって少しの差はあれど、屋根に使う漆喰をセメント質にするのは現在は主流ですし、塗りやすくするのに繊維質のものを混ぜるのはスタンダードなんですね。
お好み焼きの粉を具材にひっつきやすくするのに加えるものを「つなぎ」と言いますよね。
漆喰も同じようにこれらを「つなぎ」と呼んでいます。




混ぜていきます。

このような色、分かりやすく言えばアラジンのトースターの緑色になれば完成です。これが乾いたら真っ白になるんですね。

色はアラジンそのままです。
いっとき、姫路城の屋根が白すぎると話題になっていましたが、屋根職人や左官職人に言わせれば「今だけ」と言っていました。
漆喰は塗った直後は新庄ビックボスの歯みたいに真っ白です。しかし、すぐに真っ白ではなく白になります。
それを知っているからですね。
「上がってきまーす」と屋根の見村親方の息子の竜(タツ)君がバケツを担いでハシゴを登っていきました。